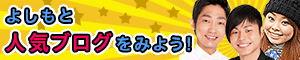結構いろいろな場所で短期間働いた経験があるが、大企業はひとつもない。客には大企業が結構たくさんいたが自分が働いたのは小さな会社ばかりだった。(て言うか、いくつかは自分で作った会社だからしかたない。)社食があるような大きな会社に勤めた経験はないが、得意先の大企業の社食には5社ぐらい行って何度か食べた経験がある。味はまあまあだが驚くほど旨い所はやはり無い。まあ値段なりの品質と味という事だろう。安いといえば安いが是非食いたいというほどのものではあるまい。労働者の空腹を最低限度満たす質というぐらいのもんだろうから喜びには欠けるが、まああんなもんだろうなと思う。大学生協の食堂を小振りにした感じだ。それ以上を望むなら自分で作るかちゃんとした金を払う必要が有るのが市場原理というものだと思う。つまり車で言うと社食の質は安い軽自動車の品質である。走るには走るがそれ以上ではないということだ。
ベトナムさんがホーチミンでよく現地の人の昼ご飯を撮影していたが、見るからにマズそうで(失礼)あれは僕には相当の拷問に見えた。ベトナム勤務は到底できそうもないし、たぶん中国勤務も駄目だと思う。そういうご苦労をしないと現地の人と仲良くなるのは難しいという部分が、異民族との接点としての困難な現実という事だろう。外国人と結婚したり一緒に長い期間生活をしたりすれば当然文化や習慣の差異に遭遇して困惑することも多いと思うが、最後は相手を人格的に信頼できるかという点に総てが収束するのだろう。だから礼儀とは同期する相手への信頼の構えのことだろうと僕は普段から思っている。
30年ぐらい前のリーマン時代の昼飯は僕も外食か弁当だった。バブルが崩壊して不景気になると多くの同僚や友人、部下は弁当屋で安い胸焼けがしそうな弁当を買っていた。そのうちコンビニの弁当とカップラーメンを食べるような部下が増えていたように思う。僕のコンビニ嫌い(というかアレルギー)は当時から始まったのだ。
僕も何度かホカホカ弁当なるものを食べたが胃腸が当時は弱かったせいもあってか胸焼けがして著しくマズいのである。若い時はマダムの愛妻弁当をずっと持って会社に行っていたから、どうしてもそれと比べると売っているものは全部総じてマズいのである。特に揚げ物はマズい。油の質がひどいのだろうと思う。一度も旨いと感じた事がない。伊勢丹のデパ地下の2000円の弁当でもやはりマズいのは、きっと防腐剤とかが入っているせいなのだろうか?新宿御苑で花見をするのに有名店のを5000円ぐらいいろいろ買って食べてみたがちっとも美味しくないのだ。あれじゃ売れないと思う。
日常生活で普段感じる幸福感というのは、「食べる(酒を飲むを含む)、眠る、風呂に入る、遊ぶ(例えば歩くとかスポーツするとか)」ぐらいが一般的で反復性がある日常動作だろう。頻度が高いほうが良いかというと適当な頻度というものがあって、多すぎると苦痛になるから少し不足気味のほうが快楽が深いような気がする。
少し欲望に対して飢餓感があったほうが有り難みが有る分喜びが大きいという事だろう。希少性があると嬉しい感じが強まるのは快楽は自動的な要素と他動的な要素が混じっている身体的な複雑な感情的反応なのだろう。
ホリエモンと2ちゃんのひろゆきが雑誌で対談していたが、高齢化社会がどんどんと進むと既存の幸福感とは別の次元の個的な価値観の幸福感が生まれてくるという。金なんて要素は今後はあまり重要ではなくて、無いなら無いで工夫次第でどうとでもなる。それは金やモノが余っている世界というのが常態化するからだ。買うから拾う、持つからシェアして分け合うという所有と使用の差異が生まれつつある。等価交換による通貨市場システムから贈与による縁故関係システムへの緩やかな移行が現れつつある。
モノ(家とか車とか)の所有などは既に無意味化してきてかえって邪魔になるケースも起こりえるから、家など無くても安い家賃の郊外や地方住宅ならシャアハウスに住むとかするとタダ同然で住んだり使ったりもできる。だからその所有のためにあくせくと長時間も働くような価値観は頭の良い若い人からは無論馬鹿にされる。100万の家賃やローンを支払うために寝ないで働かないといけない不幸な高額所得者と、月の家賃が3000円か5000円の人なら働く必要が全くないから自由な時間が何十倍も生まれて低所得でもずっと幸福感が高いということが当然起きる。過疎地の古民家をタダで借りて、自分で農業をやりながらゆっくりと子育てをするような農村、漁村へのリターンする若い世代が少しづつ増えている。都市と資本を捨てた人たちという事だ。
怠け者のほうが得をするという事で、マジに働くのは馬鹿のする事ということになりがちだ。これは僕はもうずっと20年以上も前から感じていた事で、やっと現実がそうなってきたなあと思う。だから働くのは自分の喜びのためでないとそのうち市場から裏切られると思う。資本主義の末期症状というのはきっとこういうステージの変化なのだろうと思う。拡大できなくなった時点で資本主義は死ぬ。徐々に部分から腐り始めて、次第に全体が骨格から筋肉、神経と崩れて行くプロセスを現在進行形でたどっている。日本はそのトップランナーなんだろうと僕は思う。拡大を停止した時点でシステムは維持できないのが資本の性質なのだと思う。
でも主義がどうあれ、生きるという動物の生の摂理に基本的な変化なんてないのだから、食う、寝る、遊ぶの基本を個人レベルで押さえておけば比較的快適に生き残ることは可能だろう。かつての日本の一流企業(東芝、日立、三菱重工、石川島、NEC,シャープなど)がここにきて総崩れなのは、末期症状の明白な証拠なんだろうと思う。とっくに主義の主戦場は幻想空間に移行している。それがグーグルやアップルやソフトバンクやゴールドマンという事なのだろう。集積期なベクトルが崩れて分裂的なベクトルに移行したのだ。それについて行く方法と組織を日本は見失ったということだろうと思う。残業なんて死ぬほどしてみても方法と組織ができるはずも無い事に気がついていないのだ。だから低迷が30年もずっと続いているのだろう。
人口が減少し始め労働力が減りはじめて全体の消費量が減少しても生産量は機械化が進んで増加すると需給バランスの逆方向のベクトルが生まれて、価値観の逆転減少がいたる所で始まる。
現在日本では空き家が急増している。比率で18%もあるらしい。だから今後も家賃は下がるし資産価格は下がる。値下がりする物件を持っていると損をするわけだが、不思議に新築の値下がりしやすい物件ばかりを買う人が大半で、全員が人生を棒に振るという結果になっている。1990年からもうずっと30年もそうなっているが、30年もの長いローンを組んで兎小屋を買う馬鹿ばかりいるから銀行、不動産屋、ゼネコンはそれで食っている。家や車は叩いてキャッシュで買うものだろうと思うが、そういう人は少ない。
岸田と武田の幻想論と欲望論を読む。20年以上前の対談だがズレていない。時代が追いついてきたという事だろうと思う。MOA美術館が新装オープンしたので見てきた。国宝の壷があった。(市場価格1億ぐらいらしい。)写真撮影が自由でフラッシュを炊いても怒られない。値打ちと値段について冷静に考えるには美術館は良い場所だと思う。
自分にとって毎日の生活の快楽とは具体的に何か?という結論はすぐ出ると思うが、その快楽の質を更に高めるにはやはり自分なりの努力と工夫が大事で、基本は反復と差異ということにやはりなると僕には思える。林住期のまっただ中にあって、残った時間を静かに楽しんで暮らして行こうと思う。昨日、郵便局から老齢年金の受け取りかたの指導通知というのが来た。もうそんな年齢になったということなのね。