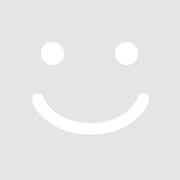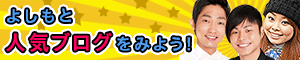|
代官山 T-SITE
平均的な美意識では満足できなくなってくると、モノに拘るようになると思う。商品企画のお仕事とかをしていると、トレンドや飽きの周期というようなものに周期性や自立性があるんじゃないかという事に気がつくだろう。これはめったに逆行などしない素直な流れのようなものだと思う。KINFORKというアメリカ雑誌があるが、その商品を天王洲アイルのSLOW HOUSEで見て買い物をしてきた。良いセールの革のソファーがあったが今度買ったAUDIのシートと同じ素材と色だった。38万が26万と3割引き。今はこれがトレンドだと思う。
正月の4日に友人を羽田に見送りに行った。途中で湘南T-SITEに寄って、鎌倉の行きつけの飲茶屋でランチを食べた。それから東京まで走って、西新宿のFUNGO DIININGに寄って、また22時まで代官山のT-SITEに行って本を買った。このように本ばかり古本も新刊もとにかく買っている。東中野の古本屋はセールで2割引だったから16冊買って1300円ぐらいだった。ツタヤでは6册で13000円ぐらいだったと思う。代官山の本屋の上には素敵なラウンジがあるので、買った本を読みながらワインを飲んだりできるお洒落な空間がある。
TSUTAYAの社長は、昔は婦人服の企画をする鈴屋のバイヤーだったから、生活全体に関してのファッションセンスが実に良い。だから商品もサービスもカッコいいミーハーテイスト満載で僕は好きだねと思う。
例えば車雑誌にカーグラフィックという月刊誌がある。日本で一番信用できる小林正太郎という人が編集をしていた雑誌だが、これの30年以上前からのバックナンバーを揃えて売っている。こういう本屋は他にはないね。
どうやら景気回復の恩恵に預かって大きく儲けた人が少しはいるのだろう。こういう時は金とクロコダイルが流行るという現象が起きる。18金のブレスレットの500万の時計とか100万、200万のクロコダイルのシューズやバッグが売れるという変な現象だ。僕も好きで昔買ったからよくわかる。
100万円のシューズとか500万円の時計なんて無駄の固まりで無意味の記号なのだけれども、そういう無意味な事をしたくなるほど気分が厭世的になる時間というのがあるんじゃないのか。
結局は人類は少しも進歩なんて実はしていないのじゃないか?物質的に豊かになったようにも思うけれども争いごとは絶えないし、貧しい人は貧しいままだしそれが減るとも思えない。
残った時間が10年だとすると、せいぜい気張って楽しんで愉快に暮らそうと思う。 |

>
- Yahoo!サービス
>
- Yahoo!ブログ
>
- 練習用